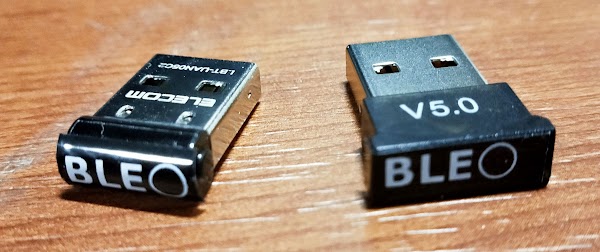Xiaomi製MijiaブランドのBLE対応スマート温度・湿度計LYWSD03MMCを購入した。ゆくゆくは高齢のお部屋を外からモニターして,その方の健康を守るのに使うことを想定。今年の夏のもっとも暑い時期は過ぎつつあるので,うまくいっても活躍してくれるのは来年以降になるとは思うが…。
ちなみに,Xiaomi Mi Flora Monitorについて調べたときにも思ったが,なぜXiaomiからの公式情報がないか見つけづらいのだろう。Mi Floraについてはまだ簡単な紹介ページが見つかったが,LYWSD03MMC についてはXiaomiの公式情報は今だに見つけられてない。なのでこの製品の英語の正式名称もわからない。パッケージも,同封されてたぺらっとしたマニュアルも全て中国語で記載されていたから。ただ,Mi Homeアプリでこの温湿度計を登録しようとしたら, “Temperature and Humidity Sensor 2” という名前が表示されていた。
以下の2つの理由でこの機種を選んだ: “ESP32デバイス向けESPHome” に書いたようにESP32ボードを利用してBLEセンサーとLANとのブリッジをしようと思っているのだが,そのファームウェアに採用することを検討しているESPHomeがこれに対応しているようであったこと。公式のサポート対象機器には含まれていないが, “Support LYWSD03MMC new mijia temp/humidity sensor · Issue #552 · esphome/feature-requests · GitHub” を読むとサポートしようとする試みがあったことがわかるし,esphome/esphome/components/xiaomi_lywsd03mmc というコンポーネントが存在しているところを見ると,もう公式にESPHomeでサポートされていると考えてよさそうだ。
追記: 9/13に公開されたバージョン1.15.0で,Xiaomi Mijia BLE Sensorsの一部としてLYWSD03MMCはMi Floraとともにサポートされた。が,公式の方法を試してもうまくいかなかった。その方法を含めて,ESPHomeからLYWSD03MMCにアクセスする手法3つをまとめた。
そして,もう1つの理由がこの手のデバイスでは安い方であったこと。Original Xiaomi Bluetooth Thermometer 2 Wireless Smart Electric Digital Hygrometer Thermometer Work With Mijia APPでバッテリなし,送料無料で$3.99 USD。つまり400円強。複数まとめて買えば単価はさらに安くなる。ESPHomeの公式のサポート対象機器にはXiaomiの他の温湿度計が列挙されているが,Xiaomi CGG1もXiaomi LYWSDCGQもお値段はずっと高い。特にCGG1はE Inkを採用しているようで,安ければ使ってみたかったのだが残念。
以下Xiaomiの提供する公式な方法以外の方法でセンサー値を利用することに関して:
- GitHub – JsBergbau/MiTemperature2: Read the values of the Xiaomi Mi Bluetooth Temperature sensor 2
- “Xiaomi Mijia LYWSD03MMC ESP32 support – Compatible devices – OpenMQTTGateway“
このLYWSD03MMCをちょっと使ってみると,以前から使ってる無印良品の温湿度計OC246W(正価税込み999円)と計測数値の齟齬がある(写真)。温度は微々たる違いなのでいいとして,湿度が劇的に違う。どらちが正しいんだろう?他に信頼できる湿度計がないからわからない。体が参るのは気温の高さよりむしろ湿度の高さだから,湿度は正確な数値が欲しいのだが…。何か違う定義の湿度量なのだろうか。 “GitHub – JsBergbau/MiTemperature2: Read the values of the Xiaomi Mi Bluetooth Temperature sensor 2” に食塩を使った補正のしかたが紹介されている。
ちなみにOC246Wについては “やじうまミニレビュー – 無印良品「携帯用温湿度計 OC246W」 – 家電 Watch” 参照。確か自分もこの記事を見て購入したはず。
Mi HomeアプリにLYWSD03MMCを登録しようとした際,3回ぐらいうまくいかなかったが,4回目ぐらいにやっとうまく行った。Mi Homeアプリには自動化の機能もあるようだが,どの程度のことができるのか,とかそういったことはまだ全然知らない。
ちなみに,Xiaomi Mi Flora Monitorは今のところFlower Careアプリでセンサー値をAndroidスマホで見ているが,これもMi Homeアプリで行うこともできるはず。双方のアプリからデータを読むことができるのか,とか,どちらのアプリが自分の目的から好都合かはまだ検討していない。